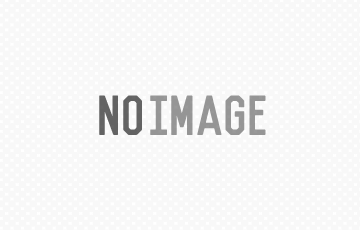目次
まだまだ残る学歴社会の影響

「会社に入社してからも、学歴は影響するのか?」
「学歴が低かったら、出世できなくなってしまうのか?」
というような疑問や不安を抱えている人は多いでしょう。
一般的に「学歴が関係するのは就職活動まで」と言われていますが、それが事実か否かは、気になるところですよね。
キャリア形成や昇進のことを考えるのであれば、学歴による影響は理解しておきたいところです。
本記事では、「会社に入社してから、学歴がもたらす影響」について詳しく解説します。
本記事を読めば、入社してからの学歴との向き合い方について、じゅうぶんな理解が得られるはずです。
就職後も、学歴による影響はあるのか?
結論から言えば、就職後に学歴が影響することは多少なりともあり得る話です。
就職活動時ほど幅広く影響を与えるわけではありませんが、かといって全くの無関係であるとは限りません。
学歴によって得をするケース、損をしてしまうケースはあります。
特に一部の企業では、入社後に学歴がかなり影響してきます。
入社後も、学歴による影響が出る会社って?

入社後、学歴が影響するのは、以下のようなケースです。
入社して数年の間
入社してから数年の間は、学歴による影響を受けることがあります。
なぜなら、キャリアが短い社員を評価する指標は限られているからです。
「会社で何を成し遂げたか」というデータがないため、実力や能力に基づいた評価をしづらいわけです。
つまり、「学歴くらいしか判断基準がないから、学歴で評価する」ということはあります。
たとえば学歴の高い人に、重要な仕事が振られたり、配属が決められたりします。
また学歴によって、給与査定が変化するということも無いとは言い切れません。
公に「この社員は学歴が高いから、給与を高くする」と表明するわけではありませんが、内々にそのような査定が行なわれることは考えられます。
もちろん全ての会社が、学歴でキャリアの短い社員を評価するわけではありません。
「資格を持っているか」、「特定の技能を持っているか」「人柄はどうか」というところで判断する場合もあります。
会社の方針や業界によっては、学歴が全く影響しないケースも多々あります。
キャリアが短い段階で学歴による影響があったとしても、いつまでもその状態が続くわけではありません。
会社での在籍年数が伸びるにつれ、学歴の影響は、少しずつ薄くなっていきます。
代わりに、実際の能力や業務成績に基づいて、評価されるようになります。
学歴による影響があったとしても、たいていは入社して数年の間だけです。
もし学歴に自信がないのであれば、高学歴よりも数倍・数十倍の実績を積み上げる必要があります。
多くの場合で最終的に重要視されるのは、学歴ではなく「会社にどのような貢献をしたか?」なのです。
大手企業では、学閥など学歴が扱いを大きく左右するケースも

大手企業に限って言えば学歴による影響が強く生じるケースも存在します。
企業によっては、能力と同じくらい、学歴や学閥を重要視することもあります。
特に高学歴が集まっている企業で、よく見られる現象です。
いわゆる「旧帝大」や「難関私学(早慶上智など)」を卒業した人が、エリートコースに乗りやすくなったりします。
もっと極端な例で言えば、学歴が高いというだけで、重要な部門に配属されたりします。
本来であれば必要になる「現場での勤務」が、免除されたりするということもあるようです。
また昇進について、学歴が大きな影響をもたらすケースもあります。
これも高学歴の人ばかりが集まっている企業で起こりがちな現象です。
こういった企業では、出身大学が一部に偏ります。
すると、「誰を昇進させるか」決定する上層部が、特定の大学出身者ばかりで構成されたりします。
たとえば上層部が「A大学」という難関大学の出身者ばかりだったとしましょう。
となると、誰を昇進させるかという議題が上がったとき「A大学」の出身者が優先的に選ばれたりします。
というような形で、企業の陣容次第では、学歴が入社後におけるキャリア形成へ影響を与えることはあります。
場合によっては、企業の有する学歴主義が、行く手を大きく阻むこともあるでしょう。
一方で、実績や成果を積み上げることにより、学歴がもたらす影響を跳ね返せることもあります。
公務員の場合

また公務員の場合、学歴が大きな影響を与えるケースもあります。
公務員は営利目的で勤務するわけではないので、「今まで挙げた実績」という判断材料が、じゅうぶんに得られないという側面があります。
公務員という職業の特性上、過去に起こした失敗が、判断材料として扱われることはあります。
ただ、「何かを成し遂げた」ということが大きな影響を持つということは稀です。
そもそも「何かを成し遂げるため、トライする」というシーン自体、ほとんどありません。
となると、勤続年数を除けば、判断材料は学歴ぐらいしかないというわけです。
具体的な影響の出方として、学歴によって昇進速度が変わったりする、というようなことは考えられます。
たとえば「同じ年数、勤務している二人のうち、一人を昇進させる」という場面があったとします。
そういった場面になると、学歴が高い方を選ぶということは充分にあり得る話です。
学歴が高くない、という場合は、昇進という側面において損をする場合があるかもしれません。
逆に言えば学歴が高い場合、多少昇進しやすいという部分もあります。
ちなみに公務員の場合、(昇進による昇給を除いて)学歴で給与が変動することはあり得ません。
なぜなら公務員の給与は、全て「俸給表」という給与水準で決められているからです。
学歴が俸給表よりも優先されることは、絶対にあり得ません。
入社後における、業務レベルでの学歴の影響
上述したとおり、入社後に、学歴が、給与や昇進などの「待遇面」への影響に加え、業務レベルまで拡大して観察してみると、細かなところで学歴の影響が出てくるシーンが散見されます。
たとえば営業職に就き、取引先とコミュニケーションを取る機会があったとします。
ときには出身大学について、話が及ぶこともあるでしょう。
「東大です」と答えられるだけで、相手に対して「この人はすごい人なんだ」と一種の錯覚資産のような印象を与えることができます。
「東大出身の彼が言うのだから、間違いはいないだろう」と判断され、こちらの言い分が通りやすくなったりする、というようなことは実際に起こり得ます。
一瞬の「信頼材料」として、学歴が影響してくるというわけです。
他にも対外的な場面であれば、学歴が役立つことは出てくるでしょう。
逆に学歴が低いということで、損をすることもないとは言い切れません。
たとえばいわゆる「Fラン大学」出身者と「旧帝大」出身者では、同じことを言ったとしても、受け手からすれば信ぴょう性は違います。
そこまでナーバスになる必要はないでしょうが、学歴がネックだと感じるのであれば、それを埋められるだけの実績や信頼は築き上げたいところです。
ただし、たいていは対外的な場面におけることであり、バックオフィス(事務などの裏方業務)で影響を受けることは、あまりないでしょう。
入社後、企業の経営層への出世するには学歴が必要なことも

ただし、経営層、つまり企業のトップを目指すときには、学歴は深く関わってくることがあります。
基本的に会社の「上層部」に行けば行くほど、学歴の影響は強まる傾向にあります。
一定の学歴以上を有していないと、経営層に入り込めないということは、しばしば聞かれる話です。
もし経営層までのキャリアアップを考えているなら、ある程度学歴が必要であると考えたほうがよいでしょう。
ときには学歴の壁は厚く、実績や成果ではどうにもならないということもありえます。
また、学歴だけでなく、出身大学が影響する場合もあります。
なぜなら経営層は、学歴による「派閥」という枠組みが力を持つ世界であるからです。
派閥は、人選やキャリア形成に対して、大きな影響力を持ちます。
たとえば、
- 国公立出身だから、次期取締役に抜擢される
- 能力はあるが、私大出身だから、取締役以上にはなれない
というようなケースが考えられます。
大手企業の幹部を見てみると、この傾向は顕著に見えてきます。
やはり無名大学の出身者はほとんどおらず。難関大学の出身者ばかりが名を連ねています。
中には学歴に頼らず、いわゆる「現場からの叩き上げ」で、トップまで上り詰める人も、いないわけではありません。
しかしそれが非常に困難であることは、言うまでもないことです。
そういったサクセスストーリーを作るのは、並大抵のことではありません。
経営層まで上り詰めたい、という人は学歴の持つ影響力を頭に入れておいた方ががよいでしょう。
転職活動における学歴の影響は?

ちなみに入社後、退職して転職活動へ移る場合も、学歴が影響することはあります。
新卒であろうと中途採用であろうと、「一定の学歴を有していない人材は採用しない」というスタンスの会社もあるくらいです。
上述した、「高学歴の人ばかりが集まっている企業」は、そのようなスタンスを取っている場合が多いです。
したがって、学歴だけで落とされるというようなことも、全くないわけではありません。
とはいえ、それは一部のケースであり、基本的に心配する必要はないでしょう。
たいていの場合では転職活動時には、新卒での就職活動時ほどの学歴による影響は生じません。
なぜなら転職活動においては、今までの実績や経験、能力などが重要視されるからです。
たとえば、
「前の会社でどのような営業成績を収めてきたか」
「前の会社では、何の業務に携わっていたのか」
「今までの経験が、入社後に活かされるか否か」
というようなところにフォーカスされます。
したがって多少学歴に物足りなさがあったとしても、実績や経験次第で、結果はいかようにも変わります。
よほど極端な転職先を目指さない限り、転職活動における学歴の影響は、小さくなると考えて問題ありません。
もし転職するのであれば、
「今の会社で何を成すか」
「前の会社で何を成してきたのか」
「今までの経験は、どのような企業であれば活かせられるのか」
というようなことを考えるほうが、はるかに重要です。
仮に学歴が低かったとしても、功績や経験によって、転職活動を有利に展開することもじゅうぶん可能です。
また転職活動は、年齢や経験年数が伸びるほど、学歴による影響も薄くなっていきます。
つまり、実績や経験、能力がさらに重要視されるということです。
まとめ
会社に入社した後も学歴の影響があるか否かは、ケースバイケースです。
高学歴なら有利に活かすことも出来ますし、低学歴であれば事前にリサーチして、影響が出る環境を避けるのも戦略の一つです。
とは言え社会人になると、実力や成果が最重要視されるようになります。
学歴が低いからといって、何かを諦める必要はありません。
一方で高学歴だからといって、油断すべきでもないでしょう。
入社後も学歴によって多少の損得はあるかもしれませんが、それよりも何かを積み重ねることの方がよほど重要なことです。
結局、基本的には学歴よりも「能力」や「実績」、「人柄」といった部分が、入社後には大切な評価のポイントとなるでしょう。
ただし一部の企業や経営層を目指す場合においては、さすがに学歴の影響は無視できなくなってきます。
学歴ひとつで、昇進やキャリア形成を阻まれることも、可能性として考えておかなければなりません。
学歴に自信がある場合は、それでも構いません。
むしろライバルが自動的に減らされるので、有利だとも考えられます。
学歴は、その人が積み上げてきた一つの努力の証です。
覆すには当然ながらそれ相応の努力が必要ですので、常に意識しながら今後のキャリアを築いていく必要があるでしょう。
![Jobby [ジョビー]](http://jobhobby.jp/wp-content/uploads/2016/08/image-2.png)