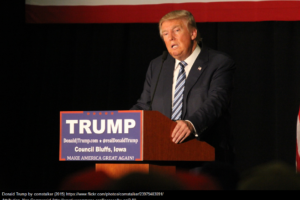2021年3月、新型コロナウイルス感染拡大の影響で生活に困っている人への新たな支援策を提示しました。
中でも注目したい支援策が、生活に困っている子育て世帯に向けて、子ども一人当たり現金5万円を支給するというものです。
ではこの支援策は、具体的にどの世帯が対象で、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?この記事では子どもへの5万円給付の支援策や、その他のコロナウイルスの支援策について分かりやすく解説します。
目次
子ども一人当たり5万円の現金給付の対策
政府によると、住民税非課税の子育て世帯を対象に、子ども一人当たり現金5万円を給付するとしています。では、住民税非課税の世帯とはどんな世帯で、これまでの支援策とはどのような違いがあるのでしょうか?
住民税非課税世帯とは?
今回の支援の対象は、生活に困窮している住民税非課税世帯とされています。
まずそもそも住民税とは、自分の住んでいる県と市町村に支払う税金のことです。働いてお金を稼ぐ人の多くが、この住民税を払うことが義務付けられています。平均として、課税所得の10%ほどが住民税として納める必要があると言われています。
しかし、住民税を払う必要がない人(=非課税対象者)もいます。具体的には以下のような人たちです。
- 生活保護受給者
- 前年の合計所得金額が135万円以下の未成年者、障がい者、寡婦・寡夫(妻・夫と離婚または死別して、その後再婚していない人)
- 前年の合計所得額が、住んでいる地方自治体に定められた額より低い人
③の対象者を具体的に言うと、独身であれば年収約100万円以下、会社員と専業主婦+子ども二人の世帯の場合、収入が約225万円以下であれば非課税対象者となります。
つまり住民税非課税世帯は、家族全員が住民税非課税者である世帯のことを指します。このような低所得の世帯が今回の給付金を受け取ることができるということです。
これまでの支援策との違い
2020年には、今回と同じような特別給付金を2回にわたって支給しましたが、その給付金を受け取れる対象はひとり親世帯のみでした。しかし今回は、子育て支援団体から両親が揃っている二人親世帯であっても困窮しているとの報告を受けたことを踏まえ、新たに対象を広げ二人親世帯にも給付金を渡すことを決定しました。
また以前であれば子ども二人目以降が3万円の給付とされていましたが、今回は一律で5万円の給付金を受け取ることができます。
子ども一人当たり5万円の現金給付のメリット・デメリット

今回の現金給付の支援策は、一見メリットが多いように感じますが、デメリットがあるもの事実です。ここでは5万円給付のメリットとデメリットを説明していきます。
5万円給付のメリット
今回の5万円給付のメリットは、給付金を受け取ることができる世帯の対象が広がったことです。今まではひとり親世帯のみが受け取れる給付金でしたが、二人親世帯でも受け取れるようになったことで、より幅広い家庭を支援できる給付金となりました。
5万円給付のデメリット
今回の給付金のデメリット・問題は、子育て世帯だけを対象としている点です。子育て世帯からは喜びの声も上がる一方、「なぜ独身の人や子どもがいない家庭には給付しないのか?」「皆が税金を払っているから、一律に給付すべきだ」「中間層だって困窮しているのに、いつも見捨てられる」といった批判の声も上がっています。
日本では、お金がないことが原因で結婚していない、または子どもを持てていないという人たちが多く存在することが分かっています。また、低所得層の少し上の層である世帯、いわゆる中間層は、全く支援を受けられず、困窮が進んでいるという現状もあります。
今回の給付金で、助けることのできる世帯の幅は広がりましたが、あくまでも“困っている人の一部”しか救済できないことが問題となっています。
その他の支援策
政府は、子どもへの現金5万円給付だけでなく、他にも様々な支援策を提示しました。ここでは3つの支援策を説明します。
コロナウイルスによる自殺の防止活動
コロナウイルスの流行により日本での自殺者数は増加しています。警視庁と厚生労働省のデータによると、2020年の自殺者数は前年より750人増加し、2万919人でした。過去10年は減少傾向にあったものの、2020年はコロナウイルスの流行によって大幅に増加してしまいました。
このような事実から政府は、孤独・孤立する人を支える活動や自殺防止活動を積極的に行うNPO法人への支援を強化するとし、約60億円の予算措置を行うとしています。具体的には、子ども食堂などの子どもの居場所作りや、女性の相談支援を行う機関を増やすことなどが挙げられています。
総合支援資金と緊急小口資金
コロナウイルスによって収入が減少し生活が困窮している人を対象に、1ヶ月最大で20万円の生活費を無利子で借りることができる「総合支援資金」という制度があります。今回の対策ではこの資金に関して、所得が少なく住民税が非課税となる人には、返済を免除することになりました。
さらに、緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、無利子で少額のお金を借りることのできる「緊急小口資金」も同様、住民税非課税者は返済を免除されます。また、これら二つの資金の申請期限を6月末までに延長しました。
住居確保給付金
職を失うなどして家賃を払うことが困難になった人に対し、家賃の金額の一部を支給する「住居確保給付金」の申請期間を、6月末までに延長しました。また長引くコロナウイルスの流行によって、一度給付金を受け取った人が再度生活に困窮した場合は、もう一度給付金を受け取れるようになりました。
まとめ
今回は、困窮世帯への子ども一人当たり5万円の給付金の制度と、その他コロナウイルスにより生活が困難になった人への支援策を紹介しました。
皆さんの中には、この記事を読むまで、政府による給付金の制度がこれだけ様々あることを知らなかったという人も多いのではないでしょうか?実際のところ、こういった給付金の制度が存在することを知らず、苦しい生活を続けている人たちがいるのも事実です。このような支援制度が多くの人たちに浸透し、給付金を受け取るべき人がきちんと受け取れるようになることを期待したいものです。
![Jobby [ジョビー]](http://jobhobby.jp/wp-content/uploads/2016/08/image-2.png)